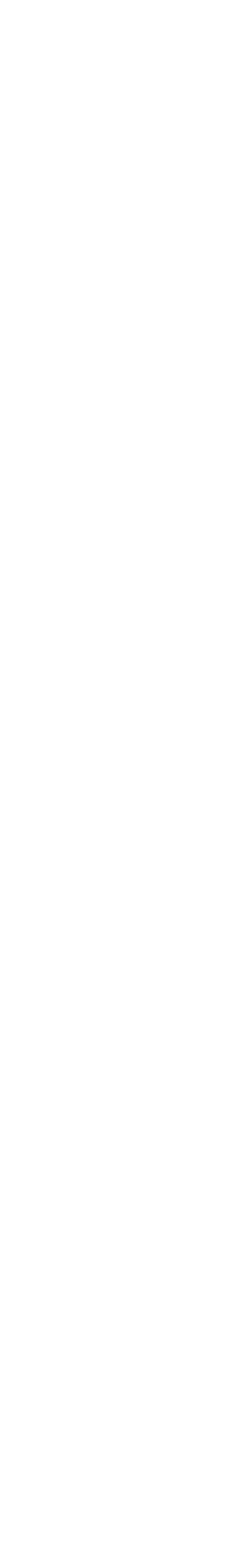氷節の歌
By Mary Kirby


フェイはまるで幽体離脱したかのように横たわり、バスティオン中で煌めきもつれ合う精神の光を遠くに眺めていた。彼女と同じサイファーたちが、メッセージを受信し、情報を高速で処理し、アーカイブのデータをまとめ上げている。もしかすると彼らはジャベリンスーツを身にまとい、冷たい夜の空を切り裂き飛行するフリーランサーやセンチネルたちとリンクしているのかもしれない。どこか覚えのある感覚だった。セノタフに飛び込んだ時と同じだ。だが、この暗闇の中でどうして、何を探しているのかがさっぱりわからない。まるで他人の行動を見ているかのようだった。
フェイは煌めく光の群れから離れ、ゲートウェイに耳を傾けた。奇妙で理解のしがたい何かを行っている具現者の奏具たちのささやきと、すべての背後に密やかに流れる「創世の賛歌」が聞こえてくる。闇の中の最も静かな場所、そのどこかにそれはあるはずだ。まるで乾きかけた泥の上に付けられた足跡のように、彼女自身の思考が残した印象の痕跡。彼女自身の精神。彼女自身の記憶が。もっと耳を澄ませばきっと…。
その時、不協和音に満ち、自己主張の激しい大きな音が彼女の集中力の殻を荒々しくかすめた。
何ですか…?フェイは身をこわばらせた。不快な音が再び響き、彼女はそれが何か真剣に聴くことにした。
誰かが近くで氷節の歌を歌っているのだ。大声で。リズムもメロディーも音程もなっていない、とてつもない音痴。その耳障りな音が氷節の歌だとフェイが気づけたのも、「氷節の寒さがやってきた!氷節の寒さがやってきた!」の繰り返しが氷節の歌のものだったからに過ぎなかった。
意識の糸を肉体に引き戻すと、フェイは閉じていた目を開き、ため息をついた。周囲の現実に焦点が合うにつれ、たった二人が横に並んで立つだけで精いっぱいなストライダーの増幅器室の姿が明らかとなったが、いまやそこには色とりどりの電球が一杯に吊るされ、薄暗がりの中で明るく光り、狭苦しく迫る壁と低く錆の浮いた天井を照らし出していた。
フェイは増幅器を停止させると、これまたなぜか雪片の紙細工に覆われていた椅子を降りた。意識を外に繋いでいた間に降り積もったらしい。例の歌と呼ぶに値しない歌は、下の貨物室から響いていた。
フェイは紙細工の飾り付けと調子はずれな歌声を頼りに、簡易キッチンへと進み、この騒ぎの主が片付け忘れた朝食の皿を押しのけてテーブルを回り込み、階段を下って、工房にいるハルークを見つけた。そこはこれまで以上に色とりどりの電球と雪片の紙細工に覆われていて、ハルークはめいっぱいの声を張り上げて歌いながら、ジャベリンを整備しているところだった。ハルークのジャベリンには驚くことに一つも飾り付けがなされていなかったが、この騒々しい元フリーランサーは、彼女が知る限り一度もシャツを身に付けたことがない素っ裸の上半身のまま、申し訳のように外の寒さを思わせるフリーランサー・イエローの特大ポンポンを付けた編み帽子を被っていた。
「フフン…フフン…雪が大地を覆い、スカーズとスコーピオンが消えたなら…それで…フフフン、フフフフン、氷節の寒さがやってきた!氷節の寒さがやってきた!」
ペンチをドライバーに持ち替えながらステップまで踏んでいる。
「ハルーク」フェイは腕を組み彼が気付くのを待った。ハルークはゆっくりとジャベリンから顔を上げて答えた。
「よう、戻ったのか!この飾り付けをどう思う?」ハルークはドライバーを握ったまま貨物室全体を指すように腕を振り回し、すこぶる良い笑顔を見せた。
「とても…」、そう言いかけたフェイの頭の中では友情と好みが激しくせめぎ合い、やがてひとつの落ち着きどころを見出した。「お祝いにふさわしいわね。この雪の紙細工はすべてあなたが作ったの?」
「大半はな。ルーキーの奴に手伝わせた分もあるかもしれない」工具を置くと、ハルークは悪くした足を休ませるように工房の壁に寄りかかった。「うるさくし過ぎたか?」
フェイはため息をついた。「量より質の問題ね」
「俺の歌が上手くなかったって言いたいのか?」ハルークは大げさにショック受けた顔を浮かべた。
「歌詞を覚えた方がいいかもしれないわ。あとは曲も。文字通り歌のほかの部分を全部」
「手厳しいな」ハルークが笑った。「ああわかった。少し声を抑えるよ」そしてどこか遠くを眺めて言った。「知ってるだろ? マイヤーランズじゃ氷節の迎え方がぜんぜん違う」
彼女はもちろん知っていた。ハルークからもう五、六度は聞かされているのだ。「前の年を振り返り、次の一年のための備えに尽くす、とても厳粛な行事なのでしょう?」
ハルークは小さく笑いを漏らした。「みんなで歌ったりなんてしないのさ。お前は何か…予定はあるのか?」
「そうね…」、彼女は言いよどんだ。分かっている。試されているのだ。セノタフを鎮めて以来、彼女の精神は彷徨いがちだ。あるいは現実が揺らいでいると言うべきか。フェイにもはっきりとは分からなかった。ハルークは心配を隠そうとして隠せていない。今日の日付、今の年、彼の名前… 彼女の記憶が確かかいつも不安げに見守っている。そして過去の祭りで何をしてきたか思い出そうとして、彼女は心を動かす何かを思い出した。「《夜明けの守護者》の氷節特番のテープを持ってるわ。今年のね。まさにこの日のためにとっておいたの」
ハルークの顔にさまざまな感情が浮かんでせめぎ合った。面白がり、たじろぎ…やがて最後に驚きが残った。「どうやって手に入れたんだ?アンティウムでも放送前だろ」
フェイは歓喜の笑みを浮かべた。これを自慢できる日を何か月も待っていたのだ。「制作部門の友人が送ってくれたの。収録は数か月前に行われていて、天候が変わるのを待っていたのよ。氷節がいつ始まるかは予測がつかないから」彼女はさらに続けようとしたが、ハルークがせわしなく杖をいじっているのに気付いた。この場を立ち去りたいというサインだ。だから答えを知っていながら聞いた。「あなたも一緒に聴きたい?」
「やめておこう」ハルークは気が咎める様子で答えた。少なくとも建前では。「どっちにしろ、もう出発しなきゃならん」続く言葉を一瞬ためらったのは、彼自身、嘘だと分かっていたからだろう。だがこれを言うのは二人にとって必要なルールだ。「だから…あとで詳しく聞かせてくれ」
「もちろんよ」、フェイもそう答えたが、そんな機会が訪れないことは明らかだった。
ハルークは頷き、互いの関係を壊すことなくフェイのラジオ番組に付き合わされる運命から逃れられたことに安堵すると、貨物室にフェイを残して、ストライダーの操縦室へと向かった。フェイは深く息をつき、静寂に身を任せた。たちまち、繋がれた電球で照らされた薄暗い貨物室が、継ぎ目からほどけていく。世界のひび割れから光が差し込み、部屋を構成する面が音の波が伝わっていくかのように沸き立った。
だがそれは一瞬のことだった。ストライダーのエンジンが大きな音を立てて始動し、脚部が動き始めるのと同時に貨物室が傾いて揺れた。ストライダーが地面を踏みしめるたびに、雷鳴のような振動が装甲を通してリズミカルに伝わり、フェイは現実に引き戻された。
お茶だ。お茶を飲もう。フェイは上のキッチンへ移動すると、湯を沸かし始めた。そして磁気テーププレーヤーを小型トランクから取り出し、テーブルに置いた。お茶が入るころには、ストライダーは目的地についていた。静まり返る船室。
フェイは再生ボタンを押した。
音楽が鳴り響く。それに合わせて鼻歌を歌っていると、ナレーターの声がテープから流れてきた。《アンティウムの精鋭ランサー達は何者にも従わない… 皇帝陛下を除いて。夜の闇と日の光の狭間に立つ者たち、それが「夜明けの守護者」。氷節が近付いている。今回、冷たい空気が我らが英雄たちにもたらすものとは一体…?》
「夜明けの守護者」のリーダー、ウォーカーの聞きなれた声がテープから流れてくると、フェイはお茶をすすりながら体を前に乗り出した。《みんな集まって。任務よ》フェイはこのウォーカーを、ジャベリンを装備した白髪混じりの自身の母親の姿でイメージするのが常だった。浅黒い肌に暗い色の髪、鋼から削り出されたかような厳めしさ。ふと、馴染みのない甲高い声がそこに加わった。《「夜明けの守護者」の皆さん、私はサイファー・ミロン》
フェイは緊張する。なぜ新しいサイファーが加わるの?過去5シーズンにわたって、ずっとサイファー・ラダがいたじゃない。ラダはフェイのお気に入りのキャラクターだ。フェイは今回の特番にはストーリーに不必要なひねりがいくつも加えられているのではと覚悟した。
「もし夢オチだったりしたら」、フェイは警戒してつぶやいた。「このテープをじかにタルシス・フォールに投げ込んでやるわ」
新登場のサイファーが続けた。《極めて重要な報せを持ってコルヴァスから直行した》
突如、金属の甲高い音がストライダー全体に響いた。貨物室のモーターが苦し気に悲鳴を上げ、ストライダーの背からエレベーターが下りてくる。フェイは顔をしかめてテープを止めた。
そして貨物室に続く手すりに視線を送った。まともな者であればジャベリン一機も入れないとわかる空間に、エレベーターから降りた二機のジャベリンが踏み入ってくる。一機目は、アーマーがピンクの炎のデカールで飾られたレンジャー。二機目は、全体がピラニックスのうろこに包まれているかのようなペイントのインターセプター。二人は緊張した様子で部屋をじっと見わたすと、頭部すれすれにぶら下げられた飾り付けを壊したり、互いにぶつかったりしないようにのろのろと歩いていたが、上手くいかない。インターセプターはすでに紙でできた雪の結晶を腕に貼り付かせ、大きすぎる金属の手でそれを取り除こうとした拍子にレンジャーの胸に肘鉄を食らわせていた。
ハルークが操縦室に向かう階段の上から大声で呼びかけた。「よし、お前ら!さっさとやるぞ!」
「ハルーク」フェイは声をかけた。彼に手すりに体をぶつけながら階段を上る手間を省かせるためだ。
ハルークはキッチンの途中で止まって答えた。「悪い悪い。お前の邪魔にならないよう、こいつらはすぐに外に出す」ハルークは階段の残りを素早く降りて貨物室へ向かった。
フェイはティーカップを指で叩きながら、向かいにある戸棚に努めて視線を向け続けた。
「くつろぎ過ぎるなよ」ハルークの声が貨物室から上ってくる。「スーツを着たらすぐに外に出る。ここでレースコースを覚えようとしたって意味がないからな」
ハルークは盛大にうなり声を上げながら自分のコロッサスに乗り込んだ。ハルークを待つ二人のランサーはさらに落ち着かなげに脚を動かしている。ハルークのジャベリンがガシャンと音を立てて工房の台を降りた。今回は少なくとも動けるだけのゲートウェイ接続を確立できた証だ。
「よし」、ヘルメットを通してハルークの声が聞こえる。「外に出たら、落ち着いてあらゆる事態に備えるんだ。いいか?」一瞬の間が空いた。「どうした、ヴァーダー?」
フェイは思い切って彼らに目をやった。
すでにいっぱいだった空間が、ハルークの巨大なコロッサスによってさらに隙間ひとつなく埋め尽くされている。その躯体には工房を出る時にうっかり壊した飾り照明が引っかかったままだ。レンジャーが挙げていた手を下ろし、不安そうに訊ねた。ヘルメットを通した声は中高音だ。「その…“あらゆる事態”とはどんな事態でしょう?いろいろと…考えられますが」
また一瞬の間。そしてハルークが答えた。フェイの知る限り、もっともそつのない声音だ。「そうだな。今後対応する。よし行くぞ、アーズリー。お前が先だ」そう言ってエレベーターに向けて頷いた。
「俺ですか?」魚のうろこ柄のインターセプターから聞こえる少し困った声は高い。「もういい。さっさと済ませよう」
ふたたびモーターが作動し、三機のジャベリンを乗せたエレベーターがさらに悲鳴じみた音を上げて動いた。そうすることで音を遮断できるとでもいうように、フェイは目をつぶった。エレベーターが止まり、きしむ音が最後に一度ストライダーにこだました。
何も聞こえない。
フェイはすでに冷たくなったお茶を置いた。大きく息を吸い、止めて待つ。ハルークはいつも忘れ物をする。そうでなければ、あのフリーランサーたちがトイレを借りに戻ってくるだろう。何かあるはず。
静寂はそのまま続き、フェイは止めていた息を吐き出すと、再生ボタンを押した。
《皇帝陛下の懸念に答えるべく…》、ランサー・ホーキングのいつも心配しているような声が流れ、フェイは苛立ちながらふたたびテープを止めた。どこかを聞き逃がしたようだ。テープを巻き戻し、もう一度再生した。
イントロの音楽がふたたび鳴り響いた。《アンティウムの精鋭ランサー達は何者にも従わない… 皇帝陛下を除いて。夜の闇と日の光の狭間に立つ者たち、それが「夜明けの守護者」。氷節が近付いている。今回、冷たい空気が我らが英雄たちにもたらすものとは一体…?》
新しいサイファーの紹介がまた始まった。《「夜明けの守護者」の皆さん…》
ストライダーの通話装置の電源が入り、大きな声が流れ出した。それを聞いてフェイはティーカップをそこに投げつけたい衝動に駆られた。
「なあ、フェイ」二重にフィルターの掛かった、どことなく申し訳なさそうなハルークの声が響く。「悪いな。操縦室まで移動して、トランスミッターの電源を入れてくれないか?信号が安定しない」
フェイはふたたびため息をついてテープを止めると、立ち上がった。キッチンの反対側にある階段は、狭い操縦室につながっている。ここはこのストライダーのどこよりもハルークの空間だが、いまはあたかも氷節が中で爆発したかのようだった。作りかけの雪の紙細工の山とモールの箱が操縦席に置かれている。制御盤はコロックスのぬいぐるみやさらに多くの色付き電球で飾られていた。軽く4メートルはあろうかという毛糸のマフラーが制御盤の下に押し込められていたが、それが一体なんのためなのか、フェイには見当もつかなかった。ハルークはこれを自分のジャベリンに巻くつもりでもいたのだろうか?フェイはトランスミッターのスイッチを見つけると、電源を入れた。通信機を使おうとそちらを向くと、通信機には紙のコロックスの切り抜きが貼り付けられている。
指にあざができそうなほど強く通信機のボタンを押し込んだ。「終わったわ」その声は、自分が意図したよりもずっと苛立って聞こえた。
通信機からふたたびひび割れた声が聞こえる。「ありがとな、フェイ!手間をかけて悪かった」
フェイは祝祭の飾りで混沌とした操縦室をもう一度眺めると、うんざりしてため息をついた。そして階段を下りてキッチンへと向かった。
テーププレーヤーを睨みつけ、また再生ボタンを押す。もっとお茶が必要だ。それにつまむ物も。なぜ菓子も準備しないでテープを聞こうとしていたのだろう?フェイはふたたびやかんを火にかけ、湯が沸くのを待った。
キッチンは静まり返っていて、音にならない音がさざ波のように戸棚や床の表面から生まれているように感じられる。その音を締め出そうと、フェイは目をきつく閉じた。目にしなければ聞こえないはずだ。「創世の賛歌」の神秘的な音色がストライダーのキッチンに響き、足から背筋へと震えが昇ってくるなか、フェイは息を止めて、ひたすら願った。
やかんの笛が大きな音で鳴り、そして途切れた。フェイは目を開き、ゆっくりと止めていた息を吐き出した。よろよろと立ち上がると新しいお茶を入れ、大げさなほどに注意してテーブルへと運んだ。まるで椅子をすり抜けて尻もちをつくことを恐れているかのような慎重さで、フェイは席についた。
そして再生ボタンを押した。
すると、それに抗議するかのようにエレベーターが悲鳴を上げ、フェイはまたすぐにテープを止めた。
ハルークの巨大なコロッサスが、足を踏み鳴らして工房へと向かっていく。
フェイが席を立ち手すりによりかかると、スーツを脱いだハルークが顔を真っ赤にして苛立っているのが見えた。頭の中で警戒音が鳴り響いた。「トラブルでもあった?」そう訊ねたフェイは、ハルークが怒りの言葉を百は飲み込んだのを見て取った。
「スーツに問題があるんだ」ハルークは空となったコロッサスに向けて怒った様子で手を振ったが、機体の動作は完璧だったはずだ。「ゲートウェイ接続がしょっちゅう切れやがる。まずは手足がロックされて、それからトランスミッターが切れた。このジャンクの塊には別の活用法を見つけなきゃな」そう言うと杖を拾い、階段を上り始めた。「コート掛けとか、ゴミ箱とか」
「きっと紙を押さえておく重しにぴったりよ」、フェイは同意した。これも二人が上手くやっていくためのルールのひとつだ。彼は階段を一段上がるたび、できうる限り足を強く踏み鳴らして苛立ちを解消している。フェイは明るく加えた。「でなければ、プランターなんかはどう?緑のシダでいっぱいにすれば、ストライダー全体が明るくなるわ」
ハルークは頭を揺らしながら馬鹿笑いをした。「そうだな。あの若造どもとは無線でやり取りを続ける」操縦室へとつながる階段スペースで足を止めたハルークは、ばつが悪そうな顔をしている。「もう一度言うが…悪かったな。いろいろと邪魔しちまって」
「本当だわ」
「埋め合わせはする!」ハルークは階段からフェイに向かって叫んだ。「フォート・タルシスに戻ったら、お前が好きなあの皮で包んだあれを買ってやる」
「2個よ」フェイはテーブルに戻って座り、テープをもう一度初めから再生した。
《アンティウムの精鋭ランサー達は何者にも従わない… 皇帝陛下を除いて。夜の闇と日の光の狭間に立つ者たち、それが「夜明けの守護者」。氷節が近付いている。今回、冷たい空気が我らが英雄たちにもたらすものとは一体…?》
《みんな集まって…》
するとまたもだ。ストライダーのエンジンが渋々といった様子で動き出し、脚部が地面を踏みしめる大きな音とともに船室が揺れ始めた。つのり続ける不満をため息にして吐き出し、フェイはまたテープを止めた。足元の床を見つめ、フェイはこれから始める同居人との言い争いについて静かに予行演習した。
床にひびが入り、そこから光が漏れ出してくる。それは不思議な冷たい光で、何かが動いているのが見えた気がした。
「悪い、フェイ」ハルークの声が通話機越しに聞こえ、幻覚は吹き飛んだ。「無線の邪魔になってる山か何かがあるんだ。マシな場所を見つけようとしてる」
フェイの頭の中で、安堵と苛立ちが少しの間せめぎ合った。どちらかが勝ったわけではない。ゆっくりと、慎重にフェイは立ち上がった。揺れる船室内を歩き、階段を上ってハルークのもとへたどり着くと、彼はストライダーを止めたところだった。ゲートウェイから切断して意識をストライダーから自身の体へと戻したハルークに向かって、フェイは制御盤からつかんだコロックスのぬいぐるみを力いっぱい投げつけた。ぬいぐるみはまっすぐハルークの胸に当たるとかすれた鳴き声を立てて、跳ねて床へと落ちた。
「フェイ!」ハルークは驚いた様子で操縦席から立ち上がりながら言った。「聞いてくれ。この埋め合わせは…」
フェイは手を振ってそれを止める。「やめて。もう十分」深呼吸して気持ちを落ち着かせる。「あなたが何をしてるか知らないけど…手伝いが必要?」
「いや。お前の邪魔はしたくない」思わず口にしてから、ハルークはしまったという顔を浮かべた。「その…すでに邪魔しちまった以上の邪魔は…」
フェイはハルークに文句を言おうと息を吸ったが、力を抜いて息を吐き出した。「もういいわ。増幅器を起動させる」
過去の祭りの日のことは思い出せないかもしれない。しかし今日のことはずっと覚えているだろう。
椅子に座り直したハルークは安堵したように見えた。ハルークは無線に身を寄せた。「よお、二人とも聞こえるか?ちょっと待ってくれ。サイファーが接続する」
フェイは増幅器へ戻ると、椅子に上った。接続が確立され、意識が幾筋にも分かれて身体からほとばしり、閉じられたストライダーの船室から…色とりどりの電球や紙の飾り付けから、広大なゲートウェイへと溶け込んでいく。暗闇の中、ストライダーに再接続するハルークとジャベリンに乗った二人の新人フリーランサーが生み出す煌めく光が見えた。フェイはそこまでたどり着くと、それらを自身の精神へと引き込んだ。すぐに、二人の目とストライダーのレンズを通して、バスティオンに雪が降るのが見えた。風に乗った氷の匂いと、ストライダーの表面に霜が降りようとしているのが感じられる。世界がすぐそこに、リアルに感じられる。
「いいわ」、フェイはフリーランサーたちに声をかけた。「始めましょう」
ゲートウェイを通して、ハルークの調子っぱずれな氷節の歌の鼻歌が聞こえ始めた。しばらくして、フェイはそれに歌詞を合わせ始めた。
John Dombrow、Ryan Cormier、Cathleen Rootsaert、Jay Watamaniuk、Karin Weekesに感謝を込めて